ジュニアテニスの他、特定のスポーツに真剣に取り組むご家庭も、多くは幼少期から小学生にかけて、色々なスポーツを経験しています。
このように、テニスの上達を目指すうえで他のスポーツを経験することは、遠回りに見えて近道でもあり、将来の子供の可能性を広げます。
なぜなら、幼児期から小学校低学年にかけて身につく「コーディネーション能力(運動の調整力)」は、どのスポーツにおいても役立ち、テニスにおいても、将来のテニス技術・スピード・安定感の土台になるからです。
この考え方は、欧米ではすでに常識で、トップ選手の多くも、幼少期には複数のスポーツをしていたことが知られています。
この記事では、保護者の方が「なぜ他のスポーツがテニスの上達につながるのか」を科学的に理解し、今日から取り入れられるヒントをまとめました。
幼少期は「神経のゴールデンエイジ」
3〜9歳の子どもの身体は、神経系が急速に発達します。
この時期は、運動神経・反応・バランス・リズム感などをコントロールする力がどんどん伸びていく、「神経のゴールデンエイジ」と呼ばれる時期です。
つまり、動きを覚える力が人生の中で最も高い時期です。
この時期に、走る・跳ぶ・投げる・転がる・止まる・反転する・バランスをとる――そんな「いろいろな動き」を経験するほど、神経が刺激されて脳と身体の連携が強化されます。
この“動きの幅”が広いほど、テニスの動作(打つ・走る・止まる・切り返すなど)を覚えるスピードも早くなります。
逆に、ひとつの動きしか知らない身体は、成長してからの対応力が低くなりやすいのです。
コーディネーション能力とは何か?
コーディネーション能力とは、簡単に言うと「思い通りに身体を動かす力」のことを言います。
具体的には、以下のような7つの力が含まれます。
- 定位能力(自分やボールの位置をつかむ力)
- バランス能力(体勢を安定させる力)
- リズム能力(動きをテンポよくつなげる力)
- 反応能力(動き出しを早くする力)
- 連結能力(体の各部をうまく連動させる力)
- 変換能力(急な変化に対応する力)
- 識別能力(道具やボールを正確に扱う力)
この7つはすべて、テニスに直結します。
・ボールの落下点を素早く予測(定位)
・ストローク時の軸の安定(バランス)
・リズミカルなフットワーク(リズム)
・反射的に動くリターン(反応)
・スイングと下半身の連動(連結)
・スライス→トップスピンの切り替え(変換)
・ラケット面を調整して当てる(識別)
感覚的な表現では「運動神経」や「センス」とひとくくりにされがちですが、テニス技術の裏にはコーディネーションがあります。これは先天的なものだけではなく、幼少期に育てることができる後天的なスキルです。
他のスポーツが、なぜテニスに効果的か
ではなぜ、他のスポーツ、野球やサッカー、水泳、体操、縄跳びなどがテニスに効果的なのでしょうか?
理由はシンプルで、「動きの引き出し」を増やすからです。
- 野球・バスケットボール → 手と目の協応、ボール感覚
- サッカー → 方向転換・タイミング・判断力
- 体操 → 体幹・バランス・柔軟性
- 水泳 → 呼吸・リズム・全身の連動
- ダンス・縄跳び → リズム・タイミング・敏捷性
これらの運動を経験した子は、テニスで「一歩目が早い」「ボールの軌道を読むのがうまい」「姿勢が崩れにくい」といった強みを発揮しやすくなります。
実際、ヨーロッパやアメリカでは、9歳くらいまでは特定の競技に絞らず、さまざまなスポーツを遊びの延長として経験させるのが主流です。
たとえばドイツの「ハイデルベルク・ボールスクール」では、6〜9歳の子どもたちにボールを使った多様な遊びをさせ、スポーツ共通の動きを先に身につけさせてから競技を選ばせます。
つまり、「早く専門化する」よりも「幅広く遊ばせる」ほうが、結果的に伸びる――というのが今の世界的な流れです。
研究でも実証されている多種運動の効果
最近の研究では、次のような結果が報告されています。
- 複数スポーツをしている子どもは、単一競技だけの子より運動協調性が高い(MDPI, 2020)
- コーディネーショントレーニングを行った幼児は、ジャンプ力・バランス・集中力まで向上した(PMC, 2024)
- ジャンプロープ(縄跳び)トレーニングは、サッカー選手のバランス・運動制御力を改善した(JSSM, 2015)
つまり、「違う動きをするほど、体が学習し、脳が成長する」。
これが科学的にも裏付けられています。
保護者ができる、家庭でのコーディネーションづくり
「忙しくていくつも習い事は無理…」
そんなご家庭でも大丈夫。日常の中でできる運動経験を少し増やすだけで効果があります。
たとえばこんな工夫です:
- 公園で鬼ごっこ(方向転換と反応力)
- 片足立ちやケンケンパ(バランス)
- 縄跳びやスキップ(リズム・連動性)
- キャッチボール(手と目の協応)
- 親子で“まねっこ体操”(鏡ゲーム)
- 小さな段差でジャンプ→片足着地(バランス+反応)
これらを「遊び」として取り入れることで、自然にコーディネーションが鍛えられます。
そして、テニスに必要な“動ける身体反応できる脳が育ちます。
専門化を急がない
保護者がよく陥るのが、「早くテニスだけに集中させた方が上達するのでは?」という考え方です。
確かに短期的にはテニスの練習量が増えますが、実はその先に壁が来ることが多いです。
なぜなら、動きのバリエーションが少ない子は、成長期にフォームを修正したり、スピード・体格が変わっても柔軟に対応できないからです。
一方で、幼児期にさまざまな運動を経験してきた子は、「姿勢のバランスが良い」「リズム感がある」「軸がぶれにくい」など、後の技術修正にも強い。
それ故、「遠回りに見えて、実は最短ルート」という表現となります。
テニスで長く結果を出す選手ほど、幼少期には「テニス以外の運動も楽しんでいた」傾向があります。
成長段階に合わせたスポーツ選択の目安
| 年齢 | 推奨アプローチ | テニスとの関わり方 |
|---|---|---|
| 3〜5歳 | 遊び+体を自由に動かす | ボールに触る・走る・投げる・転がすなど遊び中心 |
| 6〜9歳 | 複数スポーツ・遊びの中でコーディネーションを養う | テニス週1〜2回+他スポーツも経験 |
| 10歳以降 | 専門化の移行期 | テニス比率を高めつつ、基礎運動を維持 |
焦らず段階的に進めることで、10歳を過ぎてからの伸び方がまったく違ってきます。
テニスに役立つおすすめスポーツ
テニスは強打する腕力(肩)、球に追いつく脚力(フットワーク)、難しい体勢でも打ち返す体幹、しなやかな打球を生む柔軟性、長時間の試合でも耐える持久力と、全て必要になってきます。
つまり、多くのスポーツとシナジー効果(プラスの相乗効果)が期待されます。
下記によく見られる事例を挙げます。
これ以外でもそれほど神経質になる必要はなく、子供が楽しんで取り組むことが最優先です。
🏃♂️ かけっこ(陸上・短距離走)
| 項目 | ★評価 | コメント |
|---|---|---|
| 腕力 | ★★★ | 腕振りによるリズムと推進力 |
| 脚力 | ★★★★★ | 下半身の瞬発力とバランス力 |
| 体幹 | ★★★ | 姿勢保持と重心制御に重要 |
| 柔軟性 | ★★ | 可動域よりも筋出力中心 |
| 持久力 | ★★★ | 中距離要素で心肺機能も刺激 |
🏊♀️ 水泳
| 項目 | ★評価 | コメント |
|---|---|---|
| 腕力 | ★★★★★ | ストロークで全身の上肢筋群を強化 |
| 脚力 | ★★★★ | キックによる下肢筋・バランス強化 |
| 体幹 | ★★★★★ | 水中姿勢保持・体軸制御に不可欠 |
| 柔軟性 | ★★★★ | 肩・股関節の可動域向上 |
| 持久力 | ★★★★★ | 有酸素運動の代表格 |
⚾ 野球
| 項目 | ★評価 | コメント |
|---|---|---|
| 腕力 | ★★★★★ | 投球・打撃動作で上肢を総合的に使用 |
| 脚力 | ★★★ | 走塁・踏み込みで下半身を活用 |
| 体幹 | ★★★★★ | 回旋・ねじりで腹斜筋・背筋が鍛えられる |
| 柔軟性 | ★★★ | 肩・股関節の柔軟性が必要 |
| 持久力 | ★★ | 短時間集中型(瞬発力メイン) |
⚽ サッカー
| 項目 | ★評価 | コメント |
|---|---|---|
| 腕力 | ★★ | バランス補助に使う程度 |
| 脚力 | ★★★★★ | キック・ダッシュ・ステップで全域活用 |
| 体幹 | ★★★★★ | 接触・キープ・方向転換に不可欠 |
| 柔軟性 | ★★★ | 股関節可動域が重要 |
| 持久力 | ★★★★★ | 長時間走るため心肺・筋持久力ともに高い |
🤸♀️ 体操
| 項目 | ★評価 | コメント |
|---|---|---|
| 腕力 | ★★★★ | 支える・押す・引く動作が多い |
| 脚力 | ★★★★ | 着地・ジャンプ・蹴り上げでバランス強化 |
| 体幹 | ★★★★★ | バランス・静止・反転の中心 |
| 柔軟性 | ★★★★★ | 全身の可動域・しなやかさを最大化 |
| 持久力 | ★★ | 短時間集中だが筋持久的負荷あり |
💃 ダンス
| 項目 | ★評価 | コメント |
|---|---|---|
| 腕力 | ★★★ | 表現とリズムで上肢協調を鍛える |
| 脚力 | ★★★★ | ステップ・リズム動作で脚筋バランス強化 |
| 体幹 | ★★★★★ | 姿勢維持とリズムコントロールに必須 |
| 柔軟性 | ★★★★★ | 可動域・しなやかさともに重要 |
| 持久力 | ★★★★ | 曲の長さに応じて有酸素的刺激も強い |
🏀 バスケットボール
| 項目 | ★評価 | コメント |
|---|---|---|
| 腕力 | ★★★★ | シュート・パス・ドリブルで上肢制御 |
| 脚力 | ★★★★★ | ジャンプ・切り返し・加速動作中心 |
| 体幹 | ★★★★★ | フィジカル接触・姿勢保持・方向転換で重要 |
| 柔軟性 | ★★★ | 急停止・ターンに必要 |
| 持久力 | ★★★★★ | 高強度インターバルで全身の耐久力UP |
親ができるサポート
テニスを上達させたいと願う保護者にとって、「他のスポーツをやらせる」「遊ばせる」というのは一見逆方向のように見えるかもしれません。
ですが、それこそがテニス上達の最も確実な投資です。
- 幼児期は「身体を自由に動かす経験」を増やす
- コーディネーション(動きの調整力)を育てる遊びを意識する
- 他のスポーツを“寄り道”ではなく“育成の一部”と考える
- テニスの練習量よりも「動きの幅・感覚の豊かさ」を大切にする
この土台がある子ほど、10歳以降にテニス技術が一気に伸び、怪我も少なく、長く競技を続けられます。
テニスは、技術だけでは勝てないスポーツです。
反応力・判断力・バランス・リズム――それらを支えるのが、幼少期の「いろいろな動きの経験」です。
もしあなたのお子さんがまだ小学生低学年なら、今日からできる最高の準備は「たくさん動くこと」「たくさん遊ぶこと」。それが、将来テニスで大きな舞台に立つための、何よりも確かな第一歩になるはずです。
最後に、、
上記は全てテニスに向けての運動関連のコーディネーションですが、これは脳の発達にも関連しますので、学業とも無関係ではありません。そこにどれだけ振り分けるのか、興味を向かせるのかは親の采配が重要ですね。
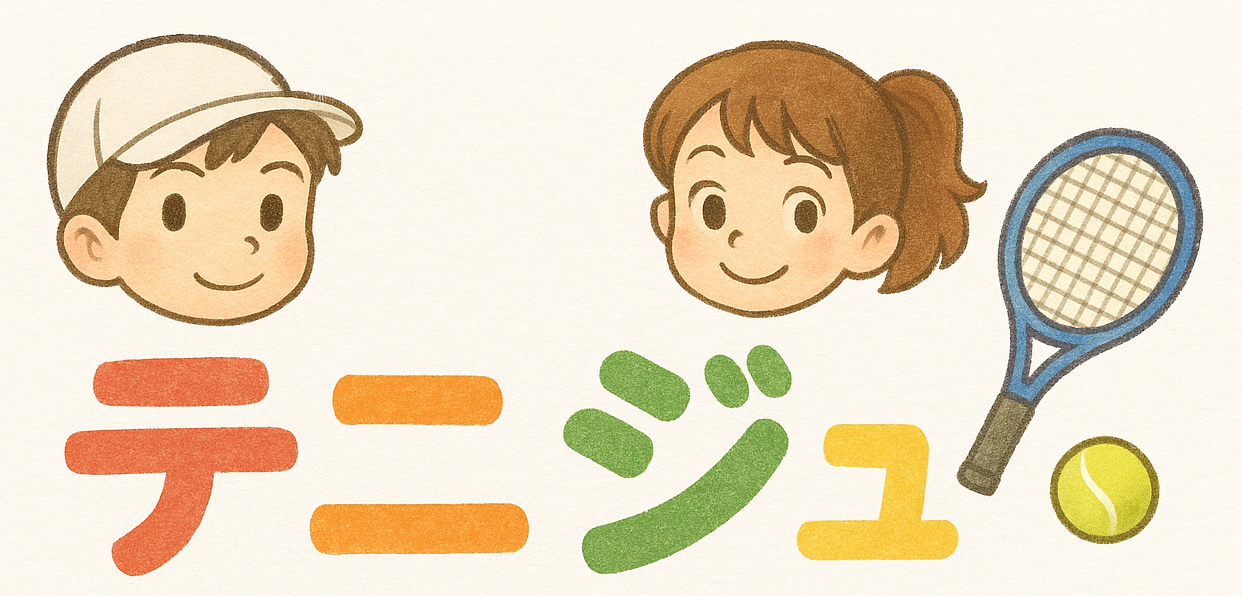


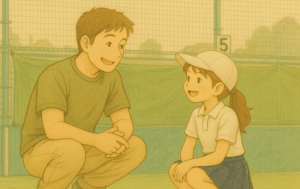



コメント