ジュニアテニスの試合は、公認、非公認問わず、長距離移動する機会が増えます。
公認大会に年間40試合程度エントリーする子も少なくないですが、このようなご家庭は関東一円、長距離移動しているはずです。この点、早朝の移動となることが多く、冬期はより一層の注意が必要となります。
朝一番の集合時間に間に合わせるために、まだ外が暗いうちから車を出し、中央道や東名、圏央道、関越道などを使って試合会場へ向かいます。普段はスムーズに移動できるルートであっても、季節が冬に近づくと状況は一気に変わります。
どんなに腕がよいドライバーも凍結だけは怖いところで、これは運転の慣れというよりも、道をよく知り、準備を怠らないことが基本でしょう。
気温の低下や天候の急変、早朝特有の路面の冷え込みは、テニスの試合で問題なく到着できるかを左右するだけでなく、最悪の場合は事故リスクを高める要因にもなります。とりわけ怖いのは試合も多い山梨方面ですかね。中央道。
早朝の試合でまだ真っ暗の山道を進みますが、都内の体感とはまったく違う気温となり、東名や圏央道などでも冬期は局所的な凍結が起こることがあります。
今回は、冬期の遠征移動に焦点をあて、早朝移動が抱える冬のリスク、関東一円の“気温が急に下がる地域”、冬期特有の注意点と、関東高速道路で特に気をつける区間などに着目し、ジュニア家庭に今一度安全な冬を過ごしていただけるよう、整理してみたいと思います。
テニスの試合は早朝移動が絡みやすい
まず大前提として、ジュニアテニスは早朝の集合が非常に多い競技です。試合の集合時間は8時~9時が多く、選手はウォーミングアップや着替えなどを含めて現地で準備する必要があります。
保護者としては、遠方になればなるほど早く出て、結果1時間以上早く着くように動くご家庭が多いでしょう。
ところが、これら日の出前〜朝7時の時間帯こそが、冬期の高速道路では最もリスクが高まる時間帯です。
気温が一日の中で最も低くなるのが早朝で、氷点下近くに下がる日も珍しくありません。雨が降っていなくても、前日の夜に濡れた路面がそのまま凍っている「ブラックアイスバーン」が最も出やすいのもこの時間帯です。
乾いているように見えて、実は凍っている。
ブレーキを踏んだ瞬間に滑り、ハンドルが効かなくなる。
これは経験したことのない人にとっては想像しにくいですが、冬の高速道路では決して珍しい現象ではありません。
関東公認は、気温の低い地域を通過する
東京は冬でも氷点下になる日は少なく、朝でも0〜4℃前後ということが多い地域です。
関東公認で高速道路を使い、中央道で山梨へ、関越道で群馬へ、圏央道で幅広く移動する場合、気温は区間ごとにかなり変わってきます。
例えば中央道。
新宿を出た時点では6〜7℃あっても、八王子付近では4℃前後、大月に向かう途中で0°~2℃まで下がるということは珍しくありません。さらに、橋梁区間やトンネル出口では周囲より1〜2℃低くなるため、実際には凍結ラインに近い場所を走っていることになります。
東名高速も同じです。
町田〜海老名付近は山裾の地形で冷えやすく、実際に毎年のようにスリップ事故が発生しています。
圏央道は標高差が大きい区間が点在するため、日陰で凍るポイントも多いです。
関越道も、新座を過ぎたあたりから一気に冷え込みます。
つまり、関東だから凍らないという感覚は冬の運転では通用しません。
突然気温が下がる日がある
冬の気候は安定しません。
前日が10℃だったのに、翌朝は2℃ということも普通にあります。
さらに、夜に雨が降ったあと晴れて冷え込む日などは、いわゆる危険な冬の朝です。
その際に、夏タイヤのままですと焦りますが、少々の寒さであれば行きますよね。
この判断が、軽装で山へ登るのと同じで怖い所です。
冬の高速道路で事故が増える典型的な条件は次の3つ。
- 前日に雨が降った
- 夜間に気温が0〜3℃まで下がった
- 明け方に晴れて放射冷却が起きた
この組み合わせだと、橋梁・高架・トンネル出口は凍ります。
しかも、日陰の区間では午前9時を過ぎても溶けないことがあります。
冬期に注意したい運転上のポイント
冬の運転で重要なのは、普通の運転をしていても滑ることがある、という前提に立つことです。スピードを出さなくても滑る。急ブレーキを踏んでいなくても滑る。
油断とは関係なく、条件が揃えば車は簡単に制御を失います。
凍りやすい場所・時間
路面が冷えやすく、凍結の定番ポイントです。
中央道の笹子トンネル出口や、東名の大和トンネル付近などは典型例。
もともとそういうことがあるとわかっているかどうかも大きなポイントとなります。
また、5〜7時は最も危険な時間帯です。
試合遠征でこの時間帯を走るなら、冬用タイヤは必須。
冬タイヤは早めに。ただ過信は禁物
早めの冬タイヤは、いざというときに非常に心強いです。
試合に合わせて、11月中に入れ替えると良いでしょう。
ただスタッドレスは“滑りにくくする”ためのもので、滑らないわけではありません。
滑るときは滑る、が定説ですから、あくまでタイヤは当然のものとして、対策は入念に。
スピードと車間距離は夏の2倍意識
凍結路や薄く濡れた路面は、制動距離が2倍以上になると言われています。
このため、前の車間距離を空けるのはもちろん、後ろの車間距離も確保したいところ。
後ろの車間距離をコントロールしたい場合、後ろに車間距離を詰めたい人を置かないことが鉄則です。
関東の高速道路で特に気をつけたい区間
関東公認視点で、「冬期に注意したい区間」を、データと道路構造の特徴からまとめます。
■ 中央道(八王子〜笹子トンネル出口付近)
- 標高差が大きく冷え込みやすい
- 橋梁が多く、部分凍結しやすい
- 早朝はほぼ毎日“凍結リスクあり”と思って良い
- 最後の笹子トンネル出口からの坂道以降は常連が混じる
山道で気温が上下することがわかります。走り慣れている車は結構なスピードで走りますので、
車間距離を十分空けて、左レーンでゆっくり行くのが良いでしょう。
特に笹子トンネル前後は、交通量・地形・気温の組み合わせで事故が多い区間です。
出口の337拍子の線が合図です。このあたりは、特に初めての際はゆっくり左レーンでおりましょう。
慣れている方はここから飛ばし気味で降りて、降りてからも甲府昭和ICまでオービスがないことをいいことに、かなりスピードを出す車が多いです。冬期は特にリスクが高くなりますので、焦らずに。
■ 東名高速(町田〜海老名)
- 山裾で冷気が溜まりやすい
- 渋滞の多い区間で追突事故も多い
- 晴れた朝でも“黒光りする路面=凍結”のことがある
東名で気を付けたいのは自他の油断。
自分の運転のみならず、冬タイヤを装着していない車の巻き込み事故に注意したいエリアです。
本格的に冬になっても、通れてしまうのでそのまま、という車が目立ちます。
特に雨が降った翌日などは危険。車間距離を取り、できれば背後に不安な車を置かない、距離を置くようにするのも一手です。
■ 圏央道(相模原・八王子・桶川周辺)
- 地形が複雑で日陰が多い
- 合流・分流が多く操作が増える
- 日中と早朝の温度差が激しい
圏央道は、季節関係なくトラック絡みの事故が本当に多い。
実際、この記事を書こうと思ったのは、13日のトラック事故、本日14日もまた事故と連発したことがきっかけです。
季節関係なく、事故が多いので避けられるのであれば、あまり通りたくない道です。
■ 関越道(練馬〜鶴ヶ島〜高崎方面)
- 新座を過ぎると気温が一気に下がる
- 霜や霧が発生しやすい
- 路面変化が急で、滑りやすい部分が点在
高崎まではいける、ことが多いのが実情ですが、まっすぐ北へ向かいますのでそりゃ気温は下がります。
いずれの高速道路でも、冬期における事故原因のトップは「前方不注意」「動静不注視」「安全不確認」「追突」「疲労・眠気」ですが、これらは冬期の気温低下”合わさることで、より重大事故になりやすい特徴があります。
帰りが上りとなる方は、帰宅時の渋滞時の追突も要注意。
時間に余裕を持つこと
すべての対策の中で、最も効果が大きいのは早めに出ることです。冬期の遠征移動では、時間に余裕をもたせることが安全を大きく左右します。
渋滞や凍結で減速しても焦らない、事故通行止めに遭っても迂回ができる、休憩を増やしても集合に間に合う、、
これら余白があるかどうかで、危険運転せずに到着できるかが決まります。
選手のコンディションを整えるうえでも、焦りながらの運転・急なスケジュール変更は避けたいところです。
だからこそ、冬期は普段より30〜60分早く出発して、前後の車間距離を保ち、余裕を持って移動することが、安全と試合への集中に直結します。
路面凍結予報を事前にチェック
比較的新しいサービスですが、日本気象株式会社が2021年より、路面凍結予測の情報提供を天気・防災サイト「お天気ナビゲータ」にて行っています。 路面凍結の発生危険度を、最大51時間先まで1時間ごとに確認することができます。
またスマートフォンアプリ「防災アラートPRO」でも情報が得られます。
下記サイトで事前にリスクを把握できます。
特に慣れていない道の場合は、どこで気温が下がるかわかりませんのでおすすめです。
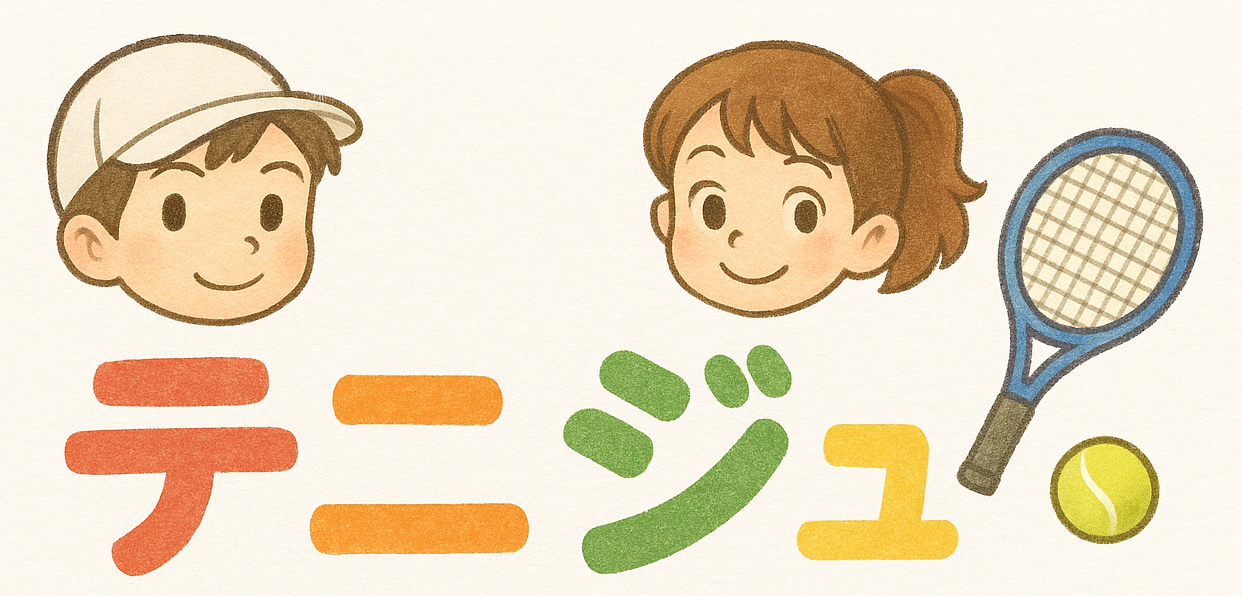


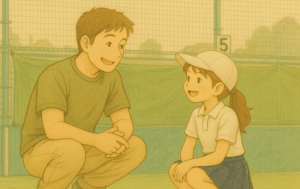



コメント