普段通っているジュニアスクールから外部の試合に始めて出る頃、年齢にして小1から小4ぐらいまでが多いでしょうか。この頃はテニスの世界の大海に出て(大会だけに)、子供にとって色々な経験が新鮮です。保護者もテニス未経験であれば同じ思いでしょう。
特に試合に出始めてから1~2年、公認大会に出るあたりまでは、試合や外部の合宿など含め、お友達を作りやすい環境にあります。
これらの友達はライバルでもありつつ、お互いテニスを通じて長い付き合いになりうる友人です。
学校はクラスが変わったり進学によって離れ離れになりがちですが、テニスはやめない限り、ある程度のレベルを維持していれば、ずっと一緒です。関東の東の果てであった翌日に、西の果てで会ったと思ったら、更にその翌週に違う会場で会ったり、、試合の機会と人数が限られているので、このような事は頻繁に起こります。
小学校の子供ですから仲良くなるのもとても早い。
家族ぐるみで仲良くなって、試合後に遊びに行ったり、一緒に合宿へ行ったり、練習を企画したり。
勝負の世界ですから勝ち負けがあったり。
何より良いのは、お友達の存在を通じて、子供がテニスの試合を好きになることが多い点です。
この点では、負けず嫌いの子供の方が良いのでしょうね。勝つためにもっと練習したいと思いますので。
副作用は、お友達の結果を確認したいがあまり、スポ人、JOP、テニスベアなど、ネットサーフィンすることですね笑。あとインスタも笑。
今の世の中は友達が多い方が良いと積極的に促す世の中ではありません。
しかし、子供が自分で動いて楽しいと思えるなら話は別。
学校では大人しくても、テニスコートの横では元気という子も多い様です。
この点、小学校のうちは親もセットですので、変な関係に比較的なりにくいです。
比較的というのは色々なご家庭がいるので、割合にして数パーセント、難しい方もいます。
しかし経験上、特に初期のころはそのような問題も含め良い関係を築きやすいです。
この初期のころ、というのはそれなりに理由があります。
選手クラスになり、レベルが上がり、小学校最終年度の公式戦が近づいてくると、周囲の雰囲気が変わり、本気モードになります。
この本気度には個人差がありますが、親子ともに、相手を罵倒するような方も一定数出てきます。
多いのはセルフジャッジやカウントを巡るトラブルです。セルフジャッジは個人の判断を尊重するのが基本で、親が口出しするのはご法度ですが、大事な試合で故意かどうかも含め、大きなミスがあればやはりトラブルになります。
初期のころは試合の勝敗以外にも練習経験や、新鮮な経験があり、社交としてのテニスの要素が強く出るのですが、
公認大会以降は敗者は基本去るのみで、バチバチ火花が散りやすくなります。
試合後のありがとうございました、の後にしていた家族間の世間話もいつしか消えて、交流の要素が弱くなり、情報交換という大人びた付き合いの側面が増えます。
でも、かつての仲間が近くにいれば、試合前に励ましあったり、一緒にアップしたりなどで、緊張もほぐれます。
応援してくれることもあるでしょう。やはりお友達がいることはプラスに繋がります。
ビギナー大会、練習マッチ、リーグ戦があるスポ人ぐらいまでは、特に交流しやすいと感じます。
特に決まりごとはありません。これらの試合では是非積極的に交流を図って、充実した未来のテニスライフを描いてください。
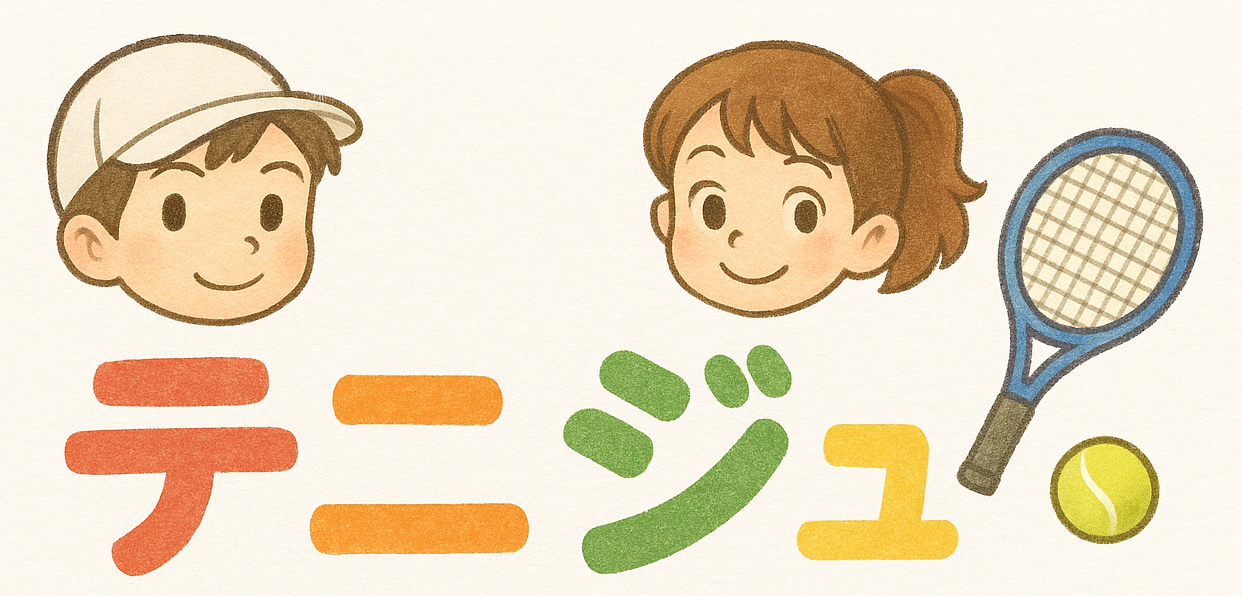
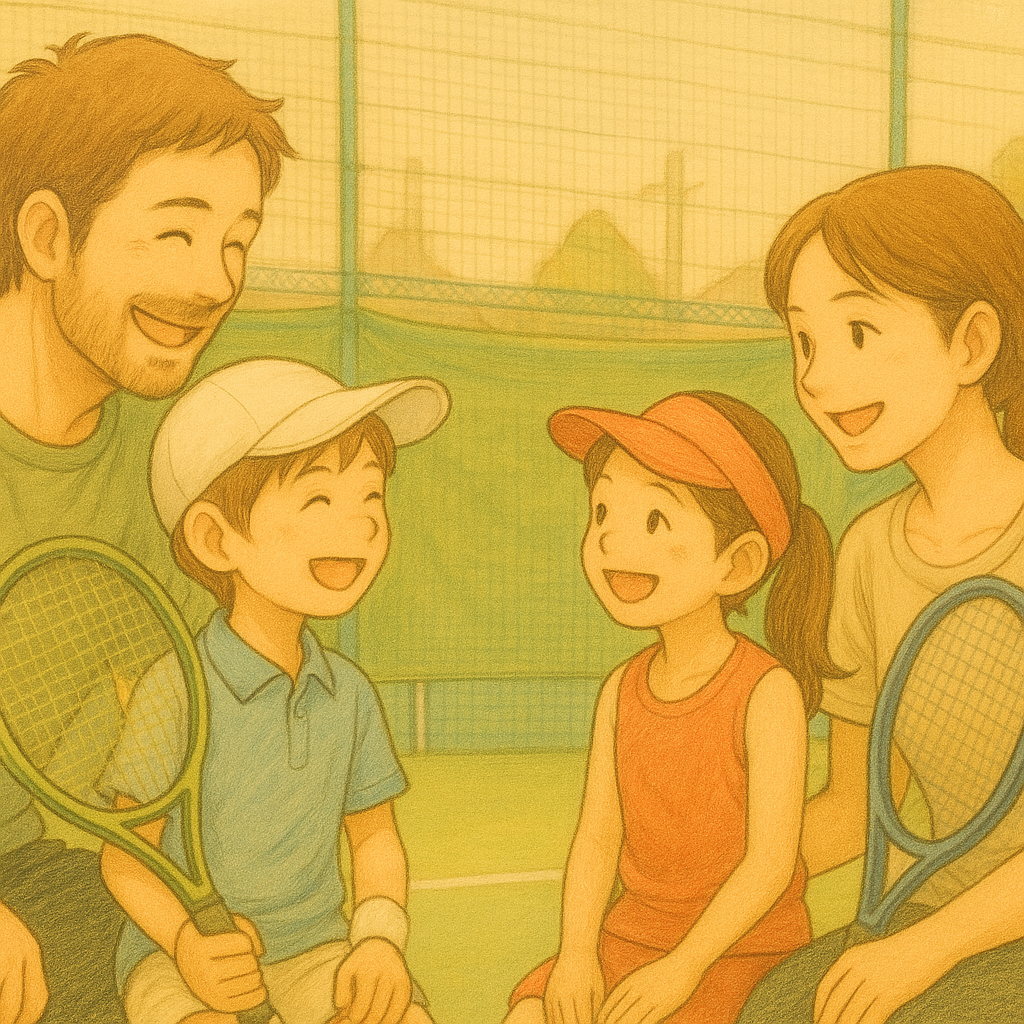


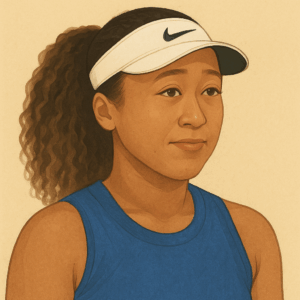
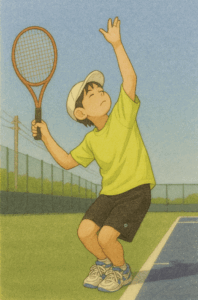
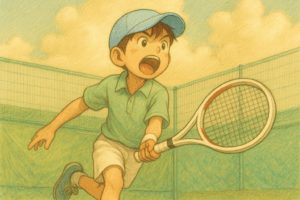


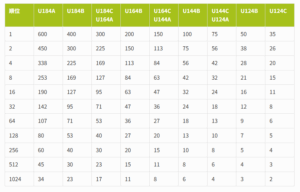
コメント