テニスは、小学生から強い子、中高生で伸びる子、その後に花開く社会人と様々です。
小学生で強ければ中高生で強いとも限りませんが、相当のアドバンテージがあるのは確かです。
小学生の間、それ以降と異なる決定的な点は、大なり小なり保護者が関係してくることです。
この点を踏まえ、小学校低学年から小学校卒業まで、実際に強くなった家庭のモデルケースを4つに分類しました。
前提共通条件
テニスでは、ポイントを稼ぐために遠方を飛び回る必要があります。
その多くは公共交通機関だけで通うことは難しく、夜遅くなることもあります。
つまり、保護者が柔軟に同伴、引率できることが必要となります。
これ以外では個別にコーチと契約してお願いするケースもありますが、それはごくごく一部の先の話。
子供の自立を促して一人で試合会場に行かせる場合、家庭方針としては良い一面もありますが、テニスにおいては回らないのが実情です。
また、一定の経済力と保護者の労力も必要です。
テニスで本気になると、結構な費用がかかります。詳しくはこちら↓
小学生のテニスに係る費用は?:通常ジュニアテニススクールと選手クラス比較 | テニジュ
またそれだけではなく、毎週子供のために時間をかける必要があります。お手伝いさんにお願いすることもできますが、お子様の心身の成長という意味では、一定の時間は必要でしょう。
この上で、関東を中心に幼少期から小学校にかけて、実際に伸びた子(関東、全国レベル想定)の家庭像、教育方針、子供の性格の実例を挙げていきます。
保護者主導型、子供自立型、家庭一丸型、コーチ信頼型に分けていきます。
保護者主導型
幼少期のテニスのきっかけは、親がテニスのきっかけを与えたか、何かしらのイベントで子供が興味をもったか(ジュニアテニスで楽しくなった)、いずれかでしょう。
やはりきっかけを作るのは親です。
そして、選手クラスへの道を検討し、そこへ向かわせるのも親でしょう。
通常のジュニアテニスクラスに通う限り、子供はそのような存在も知らないですから。
保護者主導でテニス道を邁進する場合は、いかに子供にテニスが楽しいと思わせるか、その工夫が重要となります。
その過程で自己肯定感と、昔ながらの厳しい指導との綱引きになりますが、子供のやる気を引き出す流れは、
①勝つ喜びを知り、自己肯定感に繋がり、更に努力する→ずっと強いまま
②負けても親が咎めず、結果より内容を優先して褒める→自己肯定感に繋がる
のいずれかに収束します。
これはテニスだけの話ではなく、他スポーツや勉強でも同じことですが。
小学生で強い子の多くは小6まで強いまま、ということも多いですが、これは子供が自分の意志で、その立ち位置を維持、向上しようと自ら頑張るからです。
一方で、負けた場合に親はコーチに怒られてばかりであればどうでしょうか。
これが保護者主導型の弱点で、あとは子供の性格次第で、怒られても平然としているようなタイプの子でないと、自ら努力するモチベーションは下がるでしょう。
モチベーションが下がった子供にテニスをガンガン練習させるのは困難です。
このように、保護者が主導して子供を強くしたい場合は、最初に自信を持たせて強者であり続けるように仕向けるか、上手くいかない場合は結果に対して怒らないことが肝要です。
テニススクールの常識として、「負けても怒らない」という点は使い古されたフレーズですが、なぜそうなのか?という点まで理解している家庭が強くなるのでしょう。
保護者が主導する場合は、子供の気持ちを尊重して自らは黒子となり、プロデュースする気概が必要です。
子供自立型
保護者はテニスに関して熱くなっていないが、子供がテニスに夢中になり、ひたすら練習をするケースです。
上記保護者主導型から、子供がやる気をもって転化することもあります。
まず、中学生以降も踏まえると圧倒的にこちらが優位です。
小学生の間は親が作り上げた道ですが、遅かれ早かれ、自分の足で歩いていく必要があります。
自分で決めて動く時間が増えてくるので、自分の意志でテニスの練習をしたい、質にこだわりたいという強い意志は必須です。
ただ、そのような意思をもっていても、やはり小学生。
この場合は親のサポートが足りなければ追いつきません。
適切なテニススクール、適切な練習環境、試合の調査、引率、経済力。
ここでの懸念は親の情熱です。
子供の自立を促し、好きにやらせるのも良いのですが、正しい方向に向かっているか、遭難しないように航海士は必要でしょう。勉強嫌いでテニスに没頭し、学校もさぼってテニス、それでも勝てなくて途中でテニスを急に辞めたらどうなるか。このような事を考えるのも、小学生の間は保護者の責任です。
このように、子供が自分の意志でテニスが上手くなりたいと考えている場合、非常に心身良い状態です。
保護者が練習しなさいと言わなくても良いのは非常に楽で、環境を整えれば上達の確度も高い。
一方で、その最低限のレールは、ひっそりと引いてあげる必要があります。そうしないと、昨日の東急電車のように脱線してしまいかねません。練習時間や加減も判断できない年次ですので、怪我も気を付けてあげてください。ジュニアの怪我は非常に多いです。
家庭一丸型
上記、保護者が主導するケース、子供が主導するケースに分けましたが、形はどうあれ、家庭が一丸となって迷いがない家庭は強いです。
父、母、兄弟姉妹、祖父母含め、周辺で、テニスに関する協力体制は非常に重要。
選手クラスになると練習時間が増えます。
例えば中学受験を検討していたりすると、塾との兼ね合いで迷いますよね。
ここで父母の見解が分かれると、もう結構難しい。
中学受験の勉強をしながら選手クラスで週2,3回の練習を続けることもできますが、やはり練習には制約が伴います。
どの道に進むにしても家庭間で方針が一致していれば良いのですが、分かれてしまうともう大変。
子供にもその迷いが伝わってしまいます。
この他、猛暑の夏、極寒の冬、朝早い練習、夜遅くの練習、遠征。長期休暇のレジャー。
そんなに毎回行かなくても、とか、年末年始まで公認大会出なくても、などなど。
これらは、テニスにひたすら情熱を傾けるという意味ではなく、関係者が同じ方向を向いていることが重要です。
このように、父母の姿が見えて、両者同じような考えで、詳しい家庭は強いです。
また、これは見た目だけではなく、父はしっかり稼ぎ、母はテニスでしっかり、などの分担がしっかりしている家も同様です。
コーチ信頼型
もう一点挙げておきます。
これは上記3点と排反するものではありませんが、コーチが適切な指導を行い、強い信頼関係が構築されているケース。
家庭と選手だけでは、アルカラスのようなレアケースを除き、適切な指導を継続するのはなかなか大変です。
カルロス・アルカラスの子供時代:幼少期~ジュニア期~現在の軌跡に学ぶ | テニジュ
必ず登場するコーチとの関係は非常に大事で、テニス練習において長い時間を過ごすコーチを、探して、お互いの納得し、信頼して預けられるか。
これが成就した家庭はやはり強くなります。
保護者が主導、子供が自立、家庭方針の一致、これら全ての要素に、コーチとの関係は強く影響します。
良いコーチであれば子供のモチベーションを上げうるし、家庭全体も盛り上がったり。
そうでなければ、親と揉めたり、子供がつぶれてしまったり。
練習しすぎで怪我したり、その後の人生にも影響を与えます。
コーチもそれぞれです。
テニスだけ強くなればいいのか、子供の先の事も考えればいいのか。
やはりテニスの必要十分な指導に加え、子供の人生も踏まえた指導をしてくれるのが良いコーチでしょう。
そのようなコーチもたくさんいます。是非探してみてください。
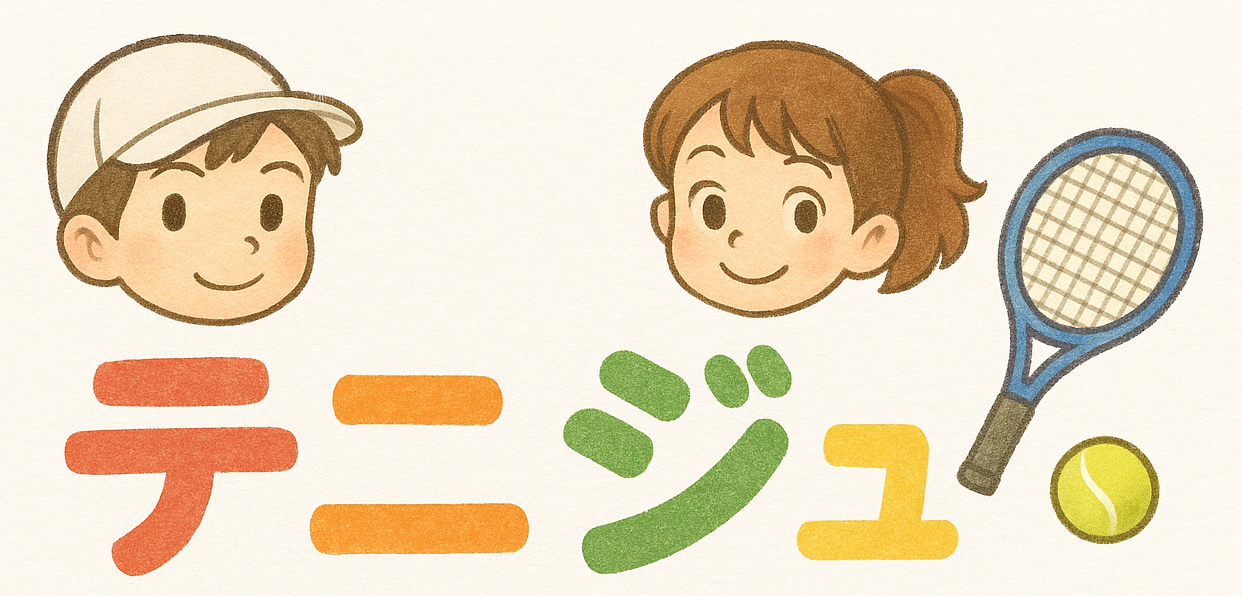
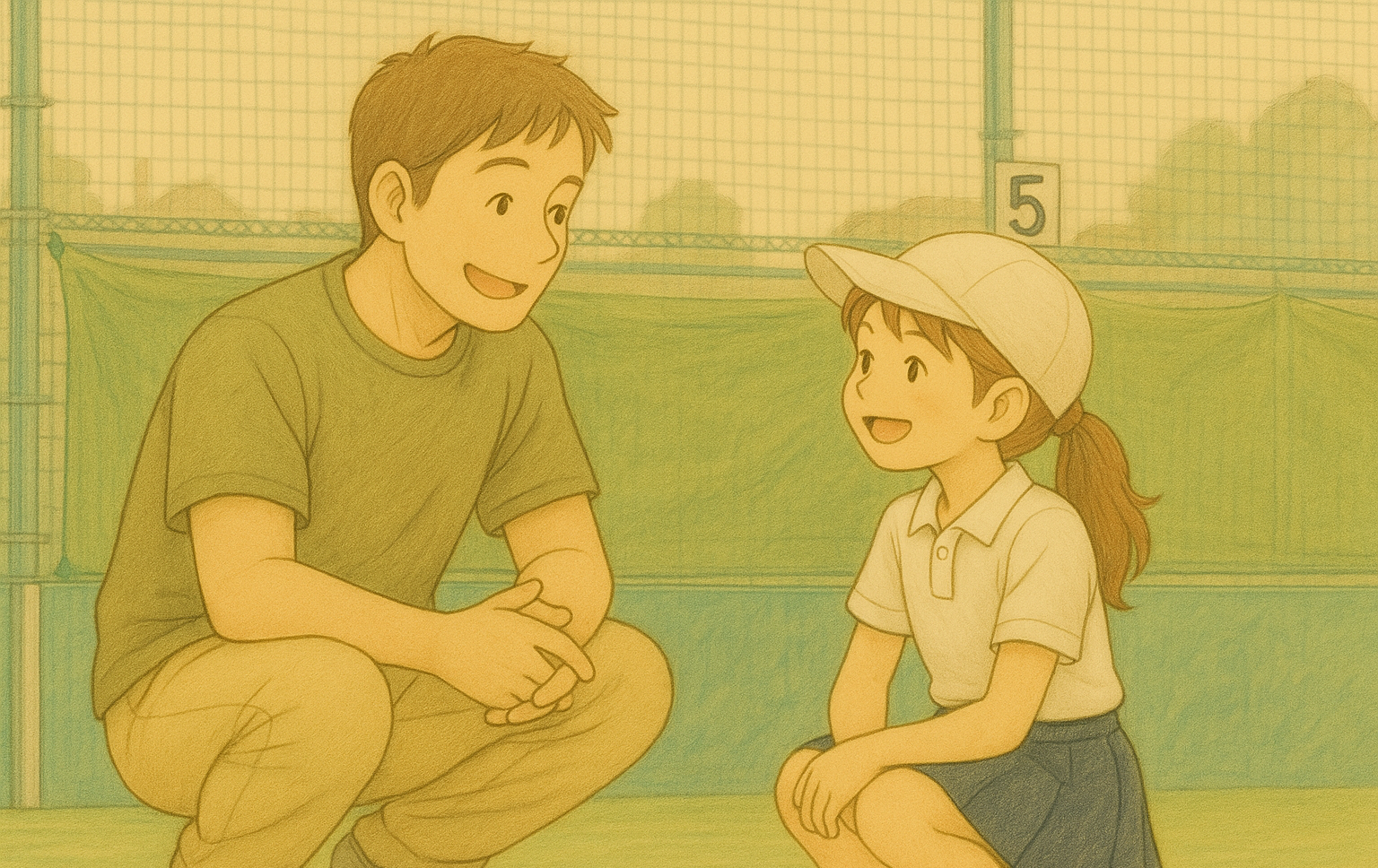



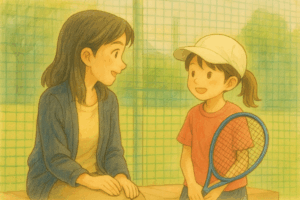
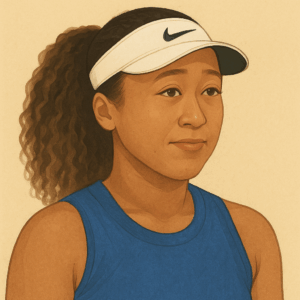
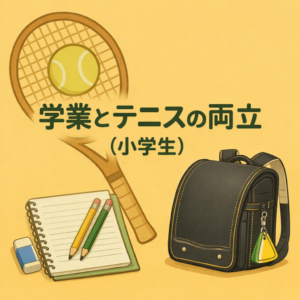
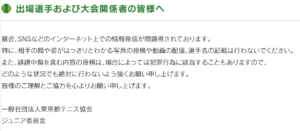
コメント