近年、ジュニアテニスの世界では、インスタグラム(Instagram)を通じて子どもの成長を記録する家庭が増えています。
練習風景や大会結果、家族での遠征記録──。
SNSの使い方が上手な親御さんも多く、まるで一つの「成長アルバム」がタイムラインに並ぶようです。
一方で、SNSはテニスを通じた交流が楽しくなる一方、トラブルや心の負担に繋がる面もあります。
「気軽に始めたつもりが、気づけばSNS中心の生活になっていた」
「フォロワーを意識して、子どもに無理をさせてしまった」
そんな声も、時代の変遷とともに、年齢を重ねるごとに徐々に大きくなっています。
インスタは情報収集面でも役立ち、楽しいツールです。
有意義に使っていただくべく、これから検討されている方向けに現況をお話しします。
Instagramの特徴(小学生のジュニアテニス)
ジュニアテニス、特に小学生においては特殊です。
保護者が子供を撮影して実名アップしていることも多く、個人情報が重要な昨今、一層のモラル意識が求められます。
子供の成長や状況に応じて周囲の受け止め方が変わる点も特徴的です。
幼児期以下であれば、アップの善し悪しはともかく、幼児がテニスを楽しむ姿に対し、周囲は概ね好意的です。
小学校低学年の、小さな大会での結果アップも同様です。
しかし、テニス選手になって本気の公認大会以降、試合結果を開示するようになると、ややセンシティブになります。
試合は勝者がいて敗者がいます。敗者は負けて泣いて悔しい思いをして、その姿をみて親も悲しい気持ちになります。
これに対して、特定の試合で相手がわかる状態で、勝者が「今まで勝てなかった相手に初めて勝てました!」など詳細をアップしてしまうとどうでしょう。
結構な率で相手方にも目が入り、あまりいい気はしませんね。これぐらい私は言われても気にしないよ、とかそういう事ではなく、一般的に世間がどう思うかです。フォロワーが多くなればなるほど、相手の気持ちもより考えて投稿すると良いでしょう。
ジュニアテニスのインスタ家庭属性
| 属性 | 特徴 | 目的 | 交流 | リスク |
|---|---|---|---|---|
| ①ライト層 | ROM専門(見るだけ) | 情報収集 | なし | 極めて低い |
| ②非開示 | 発信するが、画像は限定、友人のみ交流 | 連絡ツールとしても利用 | 限定 | 低 |
| ③画像開示 | 子供の画像を開示。名前は非開示。 | 第三者と広く交流 | 広い | 中 |
| ④画像+名前開示 | 画像と実名を開示 | 子供の売り込みも兼ねる | 制限なし | 高 |
①ライト層は見るだけ。結構います。
②~④の積極的にアップしている人にいいねしたり、用途は主に情報収集と暇つぶし。
合宿や全国大会など、様子をインスタグラムで流すことが多いのでここまではやっておいて損はなし。
②はそもそも非開示で相互フォローしている相手だけとお付き合いしたり、たまにアップしても後ろ姿だったり、個人がわからないように配慮している方。こちらも非常に多いです。インスタはメッセージ機能でやり取りできるので、テニス友達とライン替わりに使う方もいます。ここまでは諸々のリスクはあまり考えなくて大丈夫。
③は、実名はアップしないけど、画像はそのままアップして、実質的に隠していない方。
このような方もジュニアテニスでは非常に多く、③同士で交流を図り、オープンにやりとりを開示しています。
自然とその様子が①②層に流れてきて、よりフォロワーが増える図式。
やっていて楽しいですが、見えない束縛が気になることも。
ジュニアテニスにおいて、テニスの試合で実名がアップされているため、関係者間では③と④はあまり差がありません。④は完全に個人名も出しており、将来テニス選手として開花させたい保護者の意図が見え隠れします。
既に実績がある選手の多くも④で、実力が伴えば風格も帯び、突き抜けていきます。
特におすすめというものはありませんが、テニス選手としてフォロワーを広げていきたいのであれば、ある程度の実績が出てから開示を緩めても遅くないでしょう。
Instagramのメリット
1. 友達が増える、国内外のつながりが広がる
Instagramは、同じカテゴリー・地域・大会の選手たちをつなぐ力があります。
「この大会で見た子だ」「あのラケット使ってるんだ」といった共通点から、コメントやDMで交流が始まることも珍しくありません。
SNSでのつながりを通じて、試合会場でも自然に会話が生まれるようになり、テニスの世界がより楽しくなる子どももいます。
個人競技のテニスでは、孤独を感じやすい側面があるため、オンラインでの仲間づくりは子どもの安心感や継続力にもつながります。ある程度の輪が広がると、グローバルなコミュニケーションも生まれます。国際大会でその場限りとなりがちな関係も、インスタがあれば繋がります。
また、インスタを利用しているからこそ得られる情報もあります。
2. 自分のブランドを構築できる
これは少し年齢が上のジュニアに多いですが、Instagramを使って「自分をどう見せるか」を意識する選手も増えています。
「私はこういうテニスをしている」「ランキングは○○、」「目標は全国出場」など、
自分の個性や取り組み方を発信することで、いわば“ミニブランド”を築くことができます。
これは単なる自己表現ではなく、誰かしらの目に留まるきっかけにもなり得ます。
SNSの発信内容を参考にしてサポート選手を検討するメーカーやスクールも少なくありません。
「フォロワー数=影響力」とまでは言い切れませんが、
どんな姿勢でテニスと向き合っているかが伝わる投稿は、それだけで評価の対象になります。
3. 発信力が“得”につながる時代
多くのフォロワーを持つジュニア選手が自身の練習動画を継続してアップしていたところ、自社の商材を使ってもらうべく、「うちの○○を使ってみませんか?」と声をかけた──
そんなケースは実際にあります。
今の時代、情報はメディアを介さず“個人の発信”から広がります。
発信力がある選手は、それだけでチャンスに恵まれる機会が多いのは事実です。
サプライヤー契約・アンバサダー契約といった話も、SNS発信をきっかけに進むことがあります。
つまりInstagramは、努力を「見える化」して社会と接点を持つツールにもなり得るのです。
小学生のジュニアテニスで気を付けたいのは、リアルな小学生をアップして、保護者が契約を主導していることです。
テニスに関係しないものには気を付けた方が良いでしょう。その商品に問題があった時、当事者が傷を負います。
4. 記録をつけることでリズムができる
日々の練習や試合を「見える形」で残していくと、
自然と“習慣化”のリズムができます。
「毎週日曜に投稿する」「大会ごとに1枚写真を残す」──そんなルールを作るだけでも、
結果や成長を振り返る習慣につながります。
また、Instagramはアーカイブ的に使えるので、
後から振り返ると「あの時はこれが課題だった」「フォームが変わった」など、
客観的に成長を感じることができます。
“継続する喜び”を感じられる点は、テニス以外にも良い影響を与えるでしょう。
5. 子どものモチベーションにつながる
SNS上で応援コメントをもらったり、同世代の選手が頑張っている姿を見ると、
「自分も頑張ろう」という気持ちが生まれます。
特に思春期のジュニアでは、家庭やコーチからの励ましよりも、
同年代の“仲間の存在”が一番の刺激になることも多いものです。
「いいね」やコメントの数に一喜一憂するのではなく、
“応援されている実感”をモチベーションに変えられるようサポートしていけると理想的です。
Instagramのデメリット
1. デジタルタトゥーとして残る
SNSの最大の特徴は「一度出した情報は、完全には消えない」という点です。
投稿を削除すること自体寂しいですが、投稿を削除しても、スクリーンショットや引用で残ってしまうことがあります。子どもが小学生の頃に投稿した写真が、将来高校や大学の入学時に拡散される可能性もあります。
きついのは、テニスが嫌になってしまった場合。
往々にしてありえますが、このような場合に削除して消え去るのも寂しいです。
「やめても残る」という意識を持ち、投稿内容には常に注意を払うことが大切です。
2. インスタ中毒:「何か書かれてないか気になる」心理的負担
SNSは便利で楽しい反面、人と比較しやすい構造を持っています。
「誰がどの大会で勝った」「どの子がフォローを外した」など、
小さな出来事が気になってしまうことも少なくありません。
特に子どもが負けたとき、調子を落としたときには、
他人の投稿を見ること自体がストレスになることもあります。
また、何気ないコメントやスタンプが誤解を生むこともあります。
Instagramを“情報ツール”として割り切れればよいですが、小学生にそれを理解させるのは難しいでしょう。
インスタを見ている時間は、「虚無」とも言えます。
テニスで練習している時間、勉強している時間、お友達と遊ぶ時間、家族と過ごす時間、睡眠時間、通常は限られた時間を何に使うか悩むわけですが、相対的に無駄な時間になりやすい。インスタ中毒には気を付けたいところです。
3. 「記録」が目的になってしまうことも
最初は「成長記録」として始めたはずが、
いつの間にか「投稿のために試合を出す」「結果を残さないと投稿できない」と、
目的が逆転してしまうケースもあります。
これは特に、フォロワーが増え始めた頃に起きやすい現象です。
試合に負けた時に残念に思う気持ちに加えて、インスタのストレスを感じた時は危険。
SNSの更新が止まる=成績が悪い、という印象を持たれるのが怖くなってしまう。
そんな心理が、プレッシャーとして子どもにも伝わることがあります。
“頑張りを見せる場所”が“頑張らないと怖い場所”に変わってしまう。
それが、Instagramの一番の落とし穴かもしれません。
4. 実名・学校・写真から個人情報がつながるリスク
小学生のジュニアテニスでは、小学生大会を通じて「実名」「学校名」が開示され、通常の試合では「スクール名」が開示されます。画像も何らかの形で出回るので、どのあたりにいるかわかっている人が、インスタを出してしまうこととなります。
これは恐ろしく危険で、意図せず個人情報が広がるリスクがあります。
スポーツの世界では比較的オープンな文化があるとはいえ、テニスはずば抜けていると感じます。
ストーカーの危険もあれば、この日はこの家族は不在だな、と思われることも。
このあたりの危険を踏まえ、投稿する意識は必要でしょう。
親として考えたいInstagramとの付き合い方
テニスの成長を記録するツールとして、Instagramは本当に魅力的です。
ただ、使い方次第で「子どもの自信を育てる道具」にも「心を削る場所」、「ただ時間を浪費する場所」にもなります。
ここで大切なのは、親のモラルと節度でしょう。
「親のためのアカウント」ではなく、子供の事を考えた内容、見た人も有意義な内容になれば良いですね。
ごく稀に人の悪口を言う内容も見かけますが、匂わせを含め、事情はどうであれ絶対に避けた方が良いです。
一方で、有名になってきたときは法的なディフェンス(情報開示請求、弁護士)も準備しておくと良いでしょう。
今は意外と簡単に進められますが、媒体や内容で難易度が変わります。これはまた別の機会でお話しするとします。
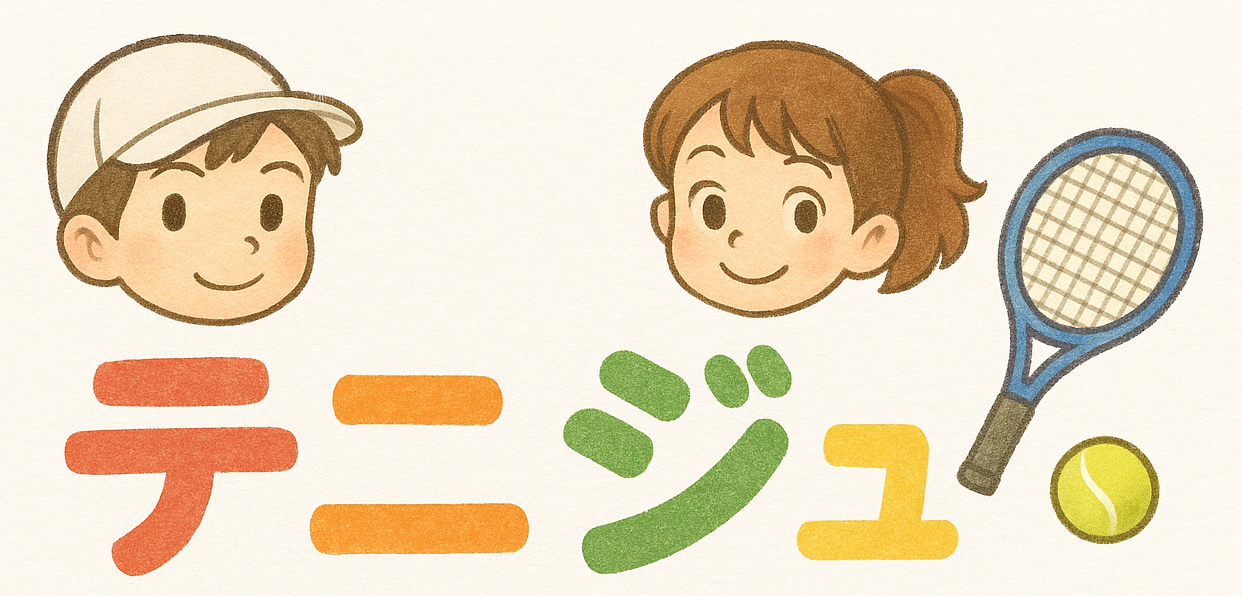
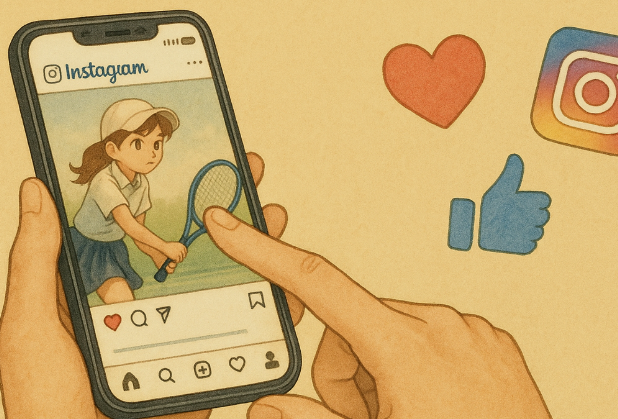



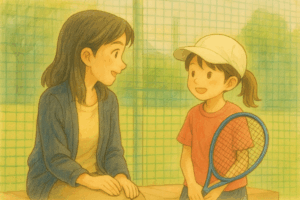
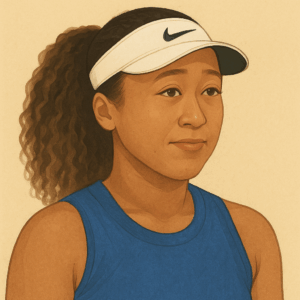
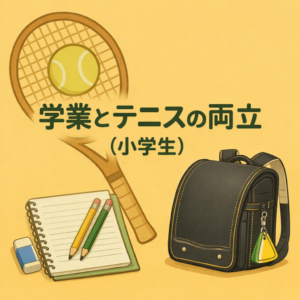
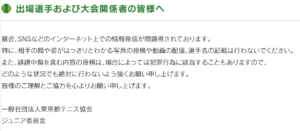
コメント