関東ジュニアでは、翌年のU12の選抜、全日本や小学生大会を見据え、開催前年の夏には既に戦いが始まっています。
どのエリアであっても、シード権を得ると非常に有利になります。逆にシードにならないと、早い段階でシードと対戦する必要があるので不利になります。このため毎年、実に熾烈なポイント争いが繰り広げられます。
関東ジュニアのランキングは過去1年を対象に、ポイントの高い上位5試合分の合計ポイントで順位が決まります。
このため、たくさん出ても、上位5つを上回らないポイントであればポイントは変わりません。
また、関東ジュニアに出場しやすい県の場合は、前年のうちに関東ジュニアに出場した選手はポイントが跳ね上がり、勝負の年に有利になり、実質的にシード権を得た形になりやすいです。
試合のグレードや年齢別でポイントが違い、知らなければ不利になる要素がたくさんあります。
経験者なら伝わるでしょうが、ネットにも出てこない暗黙知の要素が大きく、このポイント感覚を掴むまでに凡そ1年かかります。2年目~3年目で勝負の年を迎え、U12の選抜、小学生大会、関東ジュニアが一つの大きな目標となります。
この点、ポイント戦略の基本として、下記を理解しておきましょう。
・U12カテゴリとU14の選択
・ダブルエントリールールの正確な理解
・戦略的ダブルエントリーの判断
・日程被り
・平日狙い
・試合の方式、網羅
U12カテゴリとU14の選択
U12とU14ではベースとなるポイントが全く異なります。このため、カテゴリを2つ飛び越えて上のカテゴリに参加した場合、ポイントが入らないルールとなっています。
例えば、U10に参加できる10歳は、U12の大会には参加できますが、U14の大会には参加できません。
この年齢区分は暦年で行われますが、切り替えは10月が基準になります(大会による誤差はあり)。
テニスでは暦年で年齢区分され、大会の要綱に生年月日が○○年1月1日~12月31日、のように要綱に明記されています。この要綱の記載が、10月開催の大会で切り替わるという意味です。このため、上述の通り「U10に参加できる10歳は、U12の大会には参加できますが、U14の大会には参加できません。」という表記になります。概ね一斉に10月に変わるということですね。
ここで、10月にU10に参加できなくなった子は、U12だけでなくU14に参加できる権利を得ます。
U14に参加するなんて勝てないでしょ、と思われるかもしれませんが、これには大きな意味があります。
U14では、本戦に参加できるだけで、一回も勝てなくとも結構なポイントが得られます。
驚くのは、U12の4A(グレード上位の大会)と、U14の4C(グレード下位の大会)のポイントが同じという点です。
解説しておくと、4Aはまず本戦に出るのが大変、本戦では強者で溢れて一回勝つのも一苦労です。
しかし、4Cは人数が少なければ予選なしで出られますし、女子に至ってはベスト16から始まることも多いです。
このため、本人のレベルと関係ない所で、獲得ポイントの効率性が上がります。
これはポイント課金など、色々な表現で揶揄されています。
しかし、U12ではなくU14の大会を選択することはずるい作戦ではなく、ルールに則った一つの戦略とも解釈されています。公認大会で長距離運転して、初戦敗退でもU14のポイントを稼ぐ、、これでいいのかという自問自答はあるでしょうが。
確かに勝てないことが多いのですが、U14には中学生の初心者も混じり、レベルの上下幅が広がります。
このため、テニスの一定の実力がある方であれば、ドロー次第で勝てることもあります。また、相手がデフォった(休んだ)時はそれだけで二回戦進出し、稀に次も休んで二連続で上に上がることも、、
ほとんどギャンブルですが、このような形で大きなポイントをゲットすることもあります。
ただ、移動に時間を費やすこととなり、本質であるテニスの試合の機会は減ることとなるので、うまく使い分ける必要があるでしょう。
関東ジュニアランキングポイントの計算の仕組み・早見表(統合・比較用) | テニジュ
ダブルエントリールールの正確な理解
上記ポイント課金を意識した際、次にエントリー乱れうちを想定される方もいるでしょう。
しかし、本戦日程が被っている試合は、両立できません。もし二つエントリーしてしまい、そのまま放置していたら、折角得たポイントは無効となってしまいます。
このルールは、まず最初に正確に覚える必要があります。大きなところでは、下記は抑えましょう。
・要綱の日程が絶対であること
・Wエントリー自体は問題なく、ルール通り欠場届をしっかり出すこと
・予選、予備日は含まれないこと
・シングルスとダブルスの日程が分かれていることは別物として考えることができること
戦略的ダブルエントリーの判断
Wエントリーのルールを理解したら、そのうえでWエントリーすることもあるでしょう。
次に思い浮かびそうなのは、たくさん申し込んで、行けるものを選んで他は欠場したらいいじゃないかという点。
この点、これもルール上OKで、実際にポイントをためやすい一面もあります。
しかし、この多用は避けた方が良いです。正確には、よくよく空気を読み、相手方の気持ちを考えた方が良いです。
公認大会では、試合が1試合だけ、それも遠方からくる方も含まれます。
選手に共通しているのは、練習時間を大事にしていて、遠方に来た際は、①しっかり試合をしたい、もしくは②ポイントを得たい、どちらかを考えています。それにもかかわらず、簡単に欠場され、どこもかしこも欠場となることは避けた方が良いです。
この欠場傾向は感覚的に広く共有され、この人は欠場ばかりする人だと噂になるのも良くないです。
このため、欠場の乱用には気を付けた方が良いでしょう。とはいえこれはケースバイケースで、自分が圧倒的強者であれば、喜ばれることもあります。相手側の気持ちに立って、試合数や立場を踏まえて考えると良いです。
日程被り
公認大会は、夏休みなどの長期休暇期間を除き、主に土日祝日に開催されます。
ポイントのルールは絶対評価(優勝、準優勝、ベスト4,8,16,32・・・)なので、人数が少なければ圧倒的に有利となります。
この点、公認大会はお互いに日程考慮されておらず、いとも簡単に複数大会の日程が被ります。
通常の土日では2~3試合程度被ることもありますし、長期休暇中はもっと多くかぶります。
公認大会以外の有力な大会が開催されるときも同様です。
日程が被ると人も分散しますので、強者が偏り、上位進出しやすい試合が一定数出てきます。
こればかりは運ですが、日程が被っている場合は積極的にエントリーするのがおすすめです。
他の日程まで理解してくると、感覚的にもわかってきます。
平日狙い
土日祝日と、平日(長期休暇中)は、明らかにエントリー数が変わってきます。
これは、小学生の場合は多くが親の送迎で会場に来るため、長期休暇中であっても平日は参加のハードルが高くなるためです。
人数が少なれば有利な点は、日程被りと同じです。平日で更に日程が被っていれば、より有利になりますね。
これらは特に夏休みに多く見られます。
試合の方式・網羅
公認大会は実にさまざまな募集形態があります。当HPのトップページに書いていますが、
関東ジュニアのHPに記載されている年間のスケジュールを漏れなく把握したいところです。
この中には、地理的に参加者が少ない傾向がある先だったり、エントリー数が開示されず、何人エントリーしたか締め切りまでわからなかったり、募集するHPがわかりにくかったり、実に様々です。
東京を中心として、関東の端は少ない傾向があるように感じます。
このあたり、経験則として理解できますが、早めに把握したいところです。
(2025最新)関東ジュニアテニス 公認大会日程 締切逆引き版 2025年10月~2026年3月 | テニジュ
近年の傾向
これまでご紹介したのは、伝統的なポイント課金戦略ですが、近年は時代の流れを経て、変化もあります。
それは、子供の数が減っている(比例してテニスジュニア人口が減っている)点です。
かつては本戦にでるために一定の課金がマストとも言えましたが、最近は人数が減り、運営者側も寂しく感じられているのではないでしょうか。
特に女子が顕著で、エントリー数が極端に少ない先が増えてきました。
上記すべての条件が重なってくると、いきなりベスト8、ということもあります。
これはテニスをレベル別に評価するポイント制度の根幹を揺るがすもので、大きな問題です。
最初に紹介したU12orU14議論では、U14でただ数をこなしていればベスト16以上のポイント(ベスト16で24ポイント)という、U12であれば準優勝のポイント(26ポイント)に準ずるポイントを5試合揃えられます。つまり、120ポイントはU14の試合に出場さえできれば達成可能。120ポイント以上あれば、4Cであればシード近くになりえます。
このポイント事情を反映し、シードで必要なポイントも上がってくるのでしょう。
残念ながら、子供の数はこれから更に減ります。
急に寂しい話になりますが、関東のポイントの計算や試合の運営についても再考する必要が生じていくかもしれません。
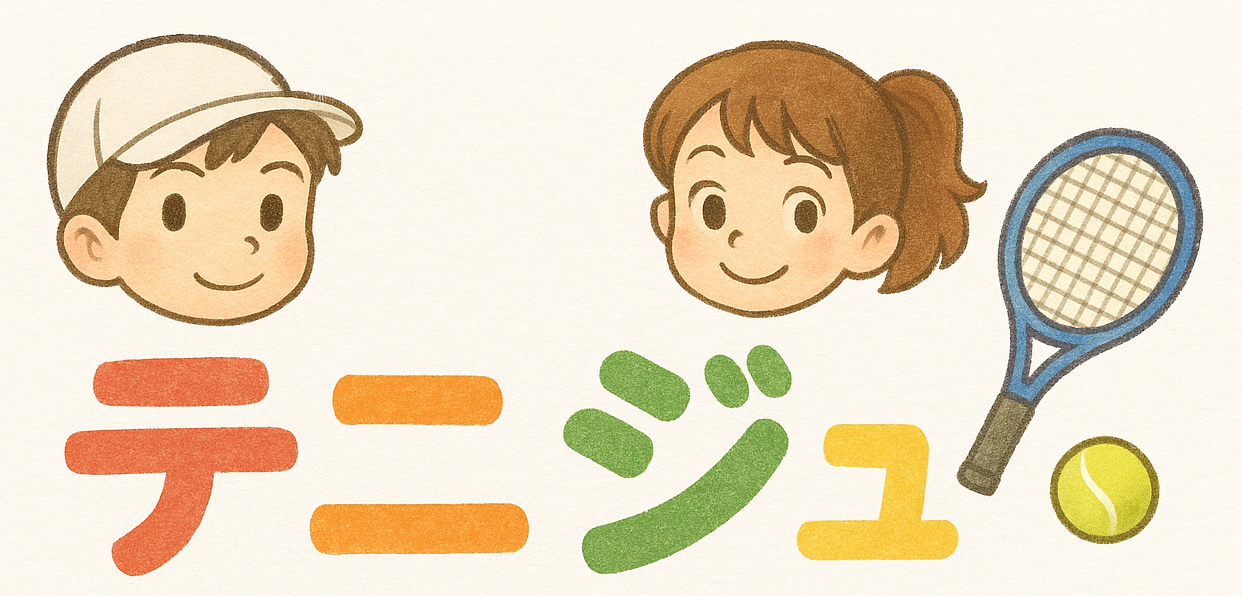


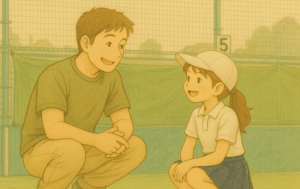



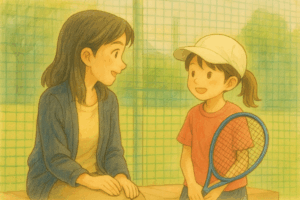
コメント